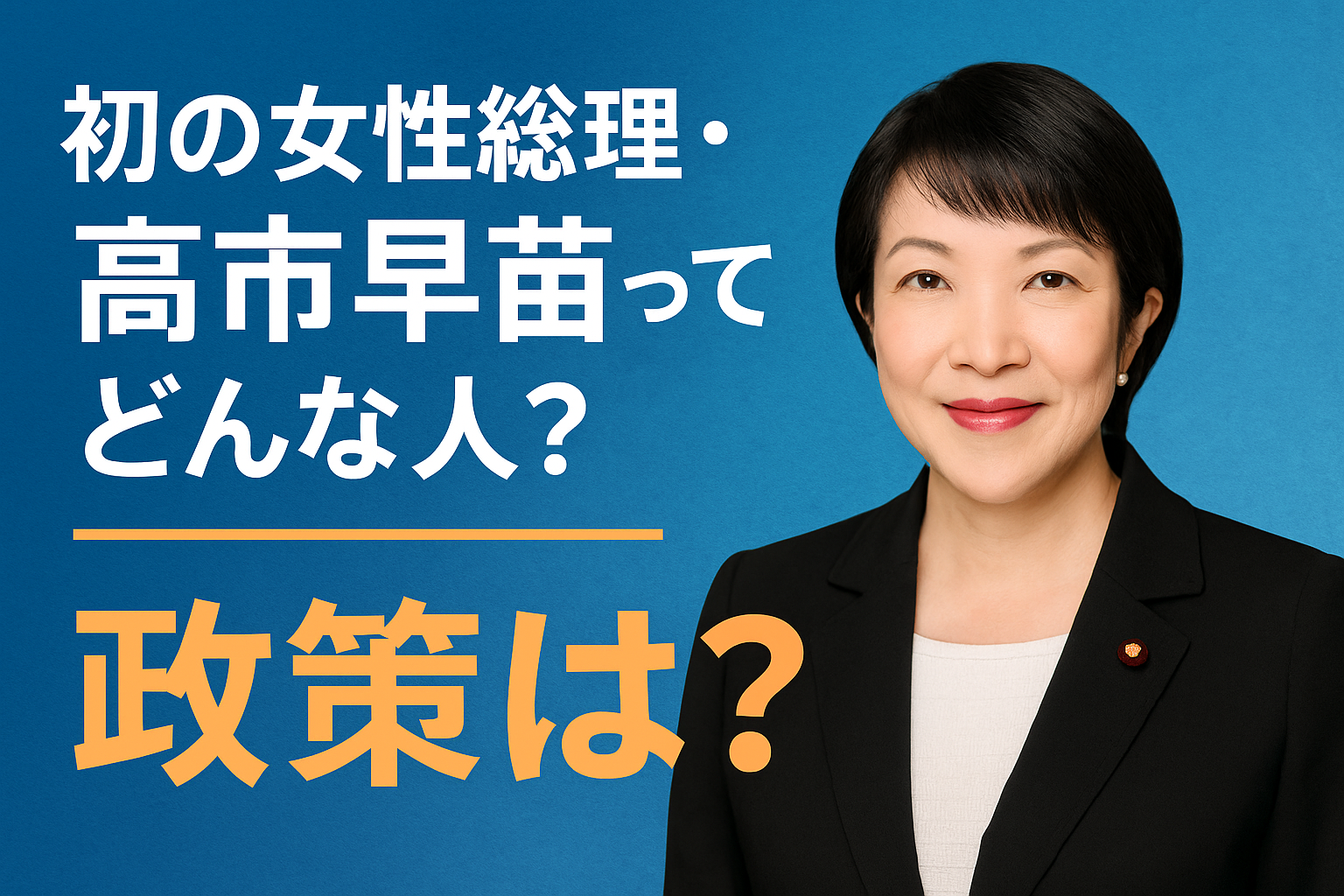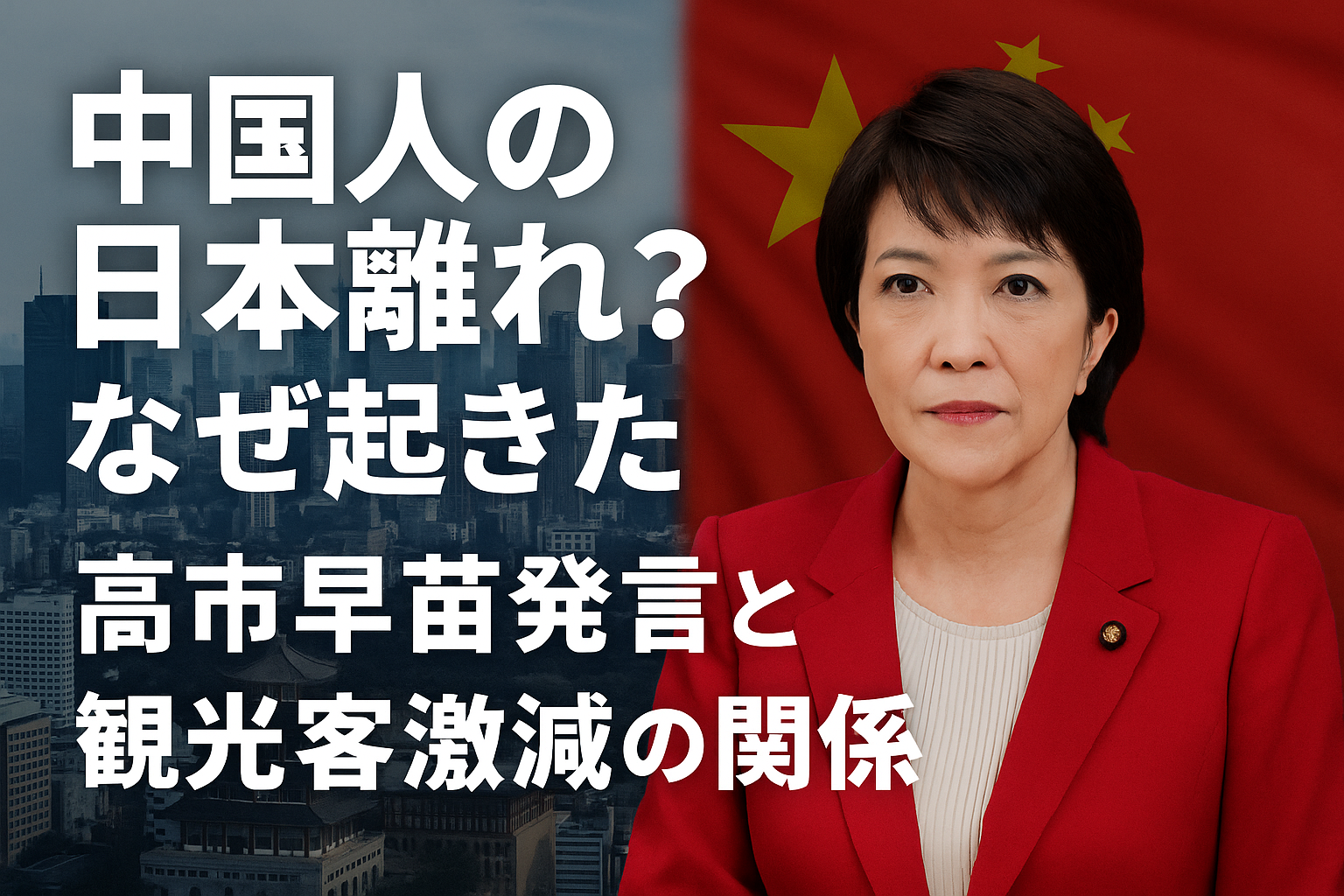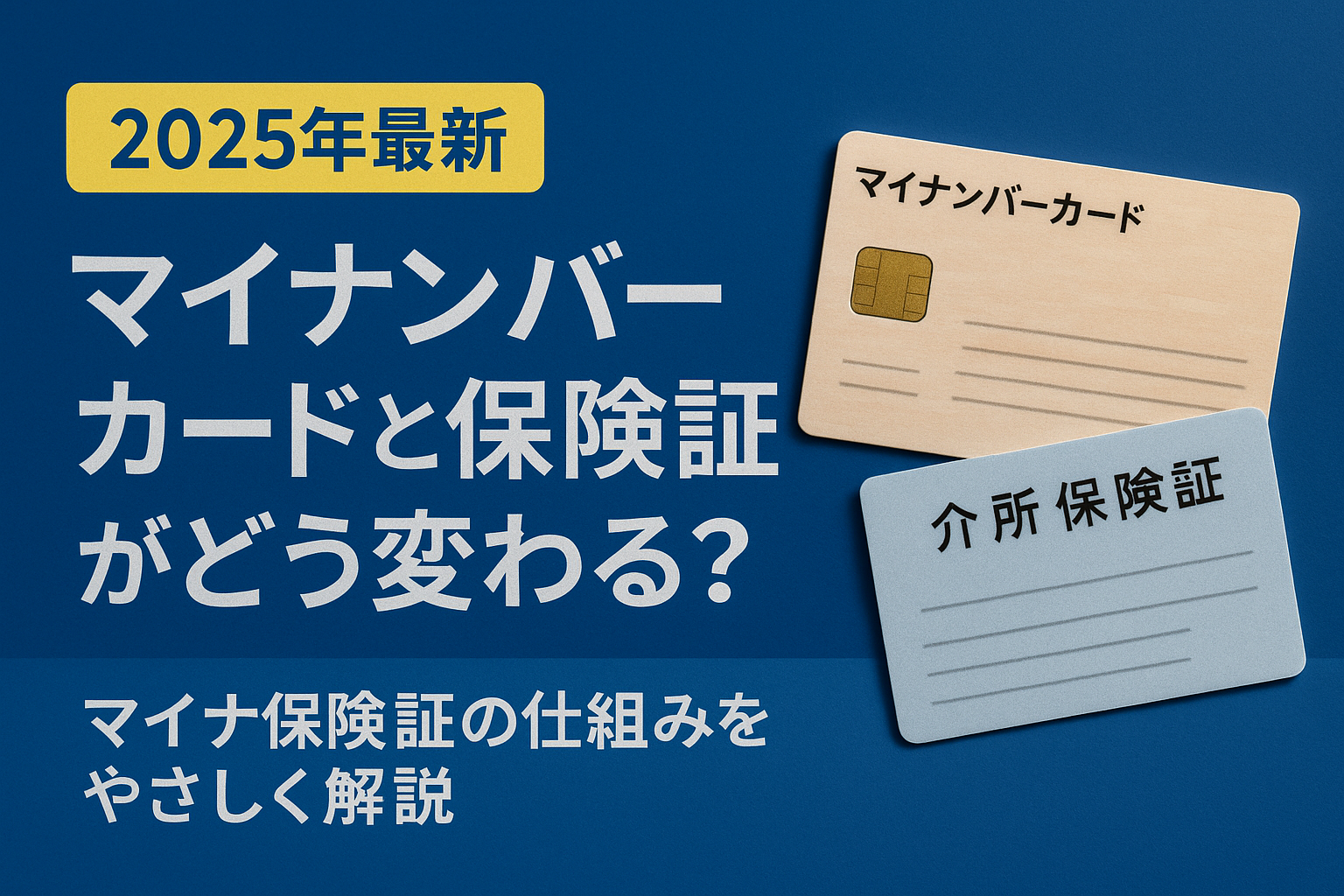高市総理が考える“給付付き税額控除”がスゴい理由

最近よく聞く「給付付き税額控除」ってなに?
最近ニュースで「高市総理が検討している“給付付き税額控除”」という言葉をよく聞きませんか?
でも、「税額控除って難しそう」「給付付きってどういう意味?」と思う人も多いはずです。
実はこの制度、お金に困っている人にも、まじめに働いている人にもプラスになるかもしれない仕組みなんです。
今回はできる限りやさしい言葉で「給付付き税額控除」がどんな制度なのかを説明します。
給付付き税額控除とは何か?
シンプルに言うと「税金の控除+お金の支給」
「給付付き税額控除(きゅうふつきぜいがくこうじょ)」とは、
税金を少なくする制度(税額控除)に、現金をもらえる仕組み(給付)をくっつけたものです。
たとえば、あなたが働いていて税金を10万円払う予定だとします。
もし「5万円の税額控除」があれば、払う税金は5万円に減ります。
でも、もしももともと税金をほとんど払っていない人(たとえば年金生活者やパートの人など)は?
この場合は控除できる税金がないので、代わりに5万円が現金で支給されるのです。
つまり、
- 税金をたくさん払っている人 → 減税される
- 税金をほとんど払っていない人 → 給付金をもらえる
という“ハイブリッド”な制度なのです。
なぜ「控除+給付」の両方が必要なの?
これまでの減税制度には、ある大きな問題がありました。
それは、税金を払っていない人には恩恵が届かないという点です。
たとえば「所得税を安くします!」と言っても、そもそも税金を払っていない人は「何も変わらない」のです。
その結果、「低所得の人が一番助けを必要としているのに、何ももらえない」という不公平が起きていました。
給付付き税額控除はその問題を解決します。
税金を払っている人も、払っていない人も、同じように支援を受けられるのです。
なぜ今「給付付き税額控除」が注目されているの?
物価が上がって、家計が苦しいから
ここ数年、食べ物や電気代など、ほとんどのものが値上がりしています。
ニュースでは「物価高(ぶっかだか)」という言葉がよく出てきますよね。
でも、給料がその分上がっていない人が多いのが現実です。
そんな中で、政府が考えているのが「給付付き税額控除」。
「働いているのに生活が苦しい」「子どもを育てるのにお金が足りない」など、まじめに頑張っている人を支える制度として注目されています。
高市総理が考える「新しい形の支援」
高市早苗総理は、これまでにも「頑張る人が報われる社会」を目指してきました。
彼女はこの制度を「減税と給付のいいとこどり」として位置づけています。
つまり、ただお金を配るだけではなく、働いている人にもちゃんとメリットがある仕組みです。
政治的にも、「低所得者への支援」と「中間層の負担軽減」の両方を同時に実現できる制度として、与野党の両方から注目されています。
給付付き税額控除で生活はどう変わるの?
誰が得をする?どんな人にメリットがあるの?
この制度で得をする人をわかりやすくまとめると、次のようになります。
- ①働いているけど、収入があまり多くない人
→ 税金の一部が戻ってくる。 - ②非課税世帯(税金をほとんど払っていない人)
→ 控除できない分が現金で支給される。 - ③子育て世帯やシングルマザー
→ 家計の支援として給付金がもらえる可能性が高い。
たとえば、年間の所得が少ない家庭が「住民税非課税」でも、給付付き税額控除なら現金を受け取れる仕組みになるため、支援の幅が広がります。
家計の変化をイメージしてみよう
今までは、税金の控除といえば「会社員の年末調整」などで少し戻ってくるだけでした。
でも、給付付き税額控除が始まると、所得が少ない人にも現金が支給される可能性があるのです。
たとえば、
- シングルマザーAさん:年収150万円 → 現金3万円支給
- フリーターBさん:年収200万円 → 税額2万円減+給付1万円
というように、働き方にかかわらず支援が届くのがポイントです。
ただし注意点もある
良いことばかりに見えるこの制度にも、いくつか課題があります。
- どこまでの収入の人を対象にするのか
- 給付額や控除額の決め方
- 財源(お金の出どころ)をどうするか
- 申請方法をどう簡単にするか
これらの点をしっかり決めないと、「不公平」や「手続きの複雑さ」が出てしまいます。
政府は今、制度設計を急ピッチで進めています。
制度はいつから始まる?今後のスケジュール
検討から実施までの流れ
今のところ、「給付付き税額控除」はまだ検討段階ですが、2025年中に制度設計が進められる見込みです。
その後、法案が国会で審議され、早ければ2026年度から一部スタートする可能性があります。
まずは「子育て世帯」や「勤労世帯(働いている低所得者)」などを中心に試験的に導入し、
うまくいけば対象を広げていく流れになりそうです。
私たちが今からできる準備
給付付き税額控除が始まったときに慌てないために、今からできることもあります。
- 自分の年収や税金の金額を確認しておく
- マイナンバーカードを活用し、手続きがスムーズにできるようにしておく
- 政府や自治体の発表をこまめにチェックする
制度が始まってから「申請が面倒でチャンスを逃した!」ということがないように、
情報を早めに知っておくことが大切です。
給付付き税額控除のメリットと課題をまとめて比較
| 観点 | メリット | 課題 |
|---|---|---|
| 家計への効果 | 手取りが増える/給付がある | 財源の確保が必要 |
| 公平性 | 働く人も働いていない人も支援対象 | 所得の線引きが難しい |
| 手続き | 自動給付なら便利 | 申請方式だと手間がかかる |
| 政治的効果 | 国民の不満緩和につながる | 維持費用が大きい |
他の国ではどうなっているの?
アメリカやカナダなどでは、似たような制度がすでにあります。
たとえばアメリカの「EITC(勤労税額控除)」は、働く人の所得が低いほど給付が大きくなる仕組みです。
この制度によって、多くの家庭が貧困から抜け出したというデータもあります。
日本もそれを参考にして、「頑張る人を支える制度」を目指しているのです。
まとめ — あなたの生活を変えるかもしれない「給付付き税額控除」
「給付付き税額控除」は、税金を払っていない人にも支援が届く新しい制度です。
高市総理が目指すのは、「働く人が報われる社会」。
この制度が実現すれば、低所得者や中間層の家計が少しでも楽になる可能性があります。
もちろん、まだ課題も多く、すぐには実現しないかもしれません。
でも、知っておくだけで将来の制度変更に備えられます。
あなたの家庭にも関係する制度かもしれません。今後のニュースをぜひチェックしてみてください。