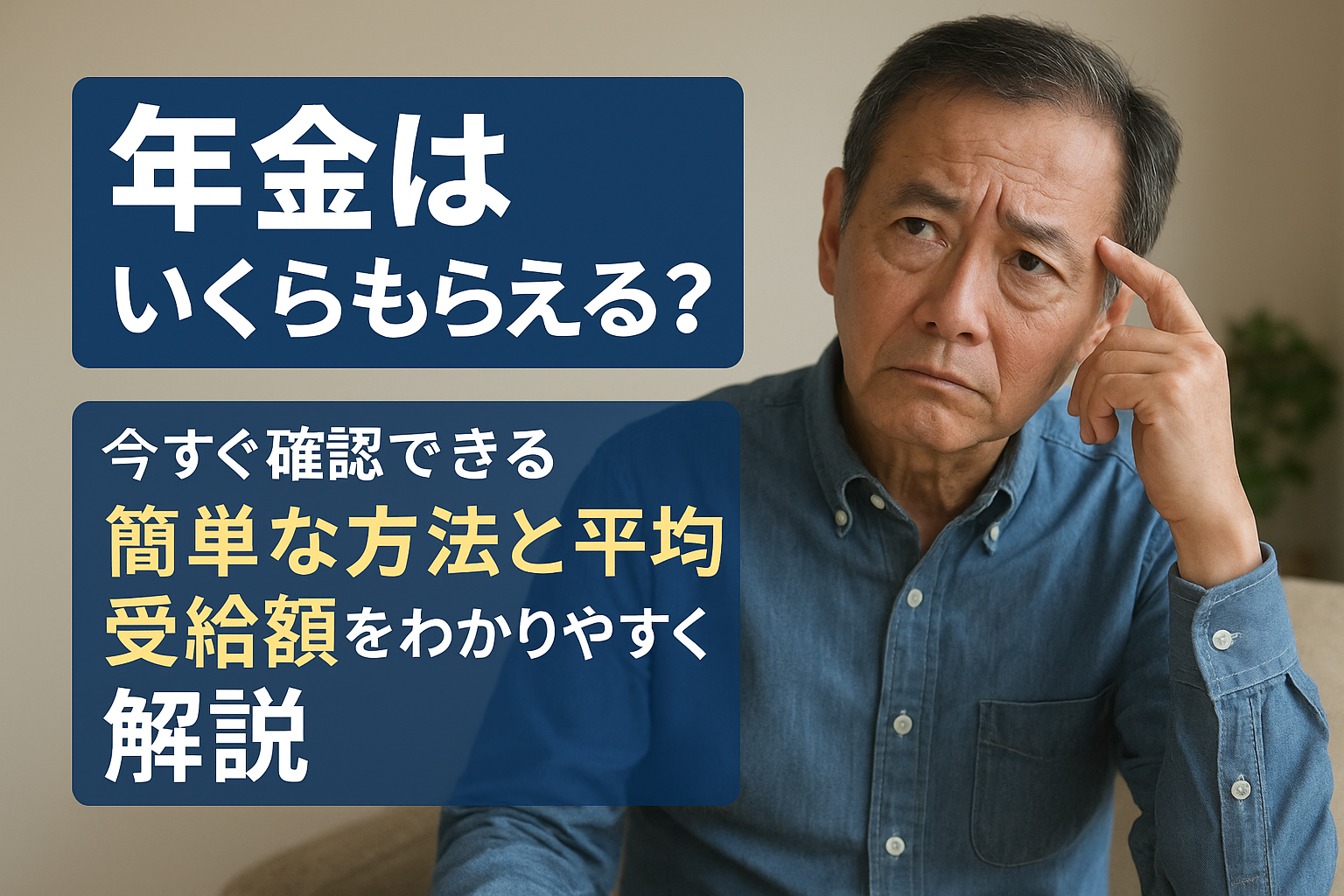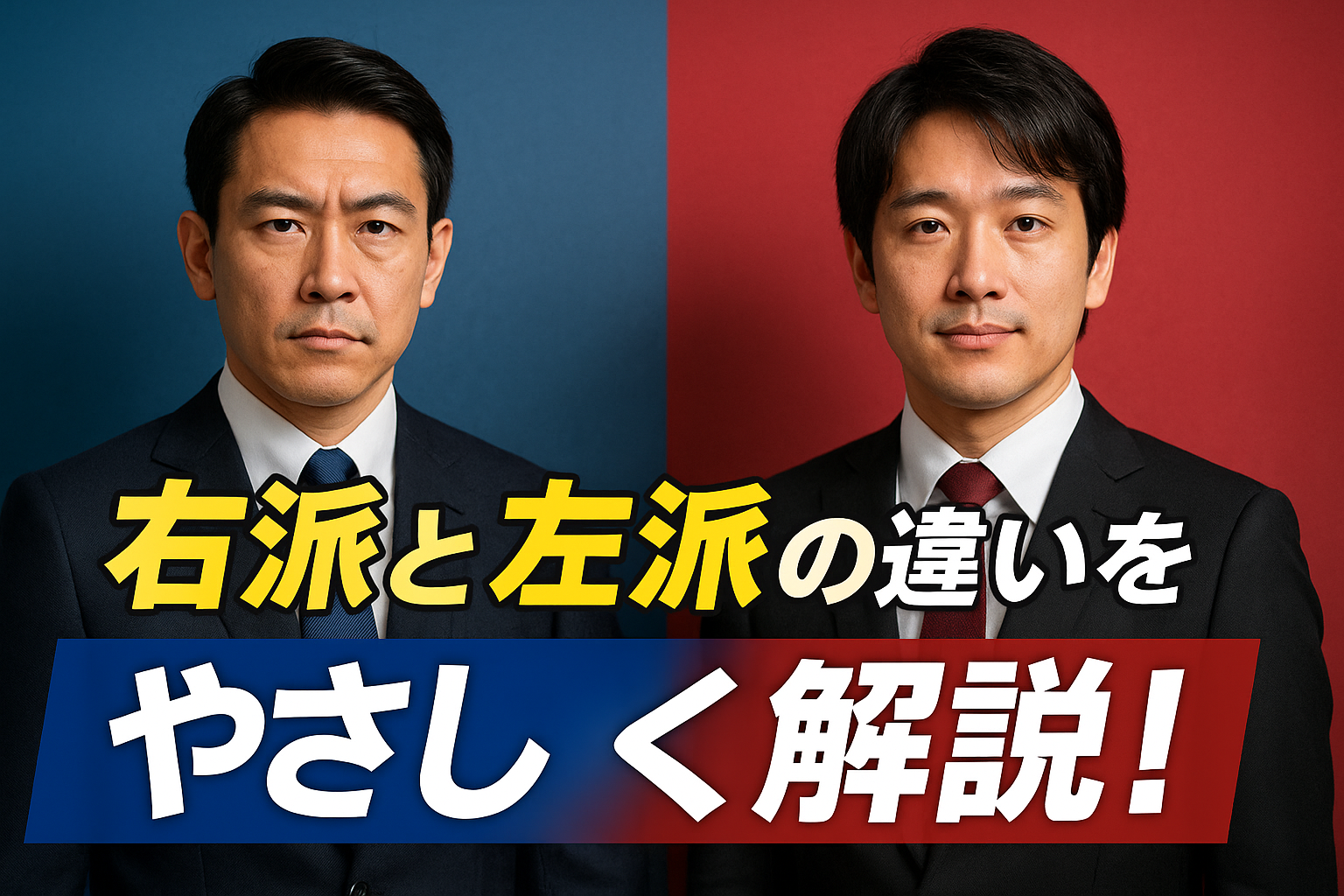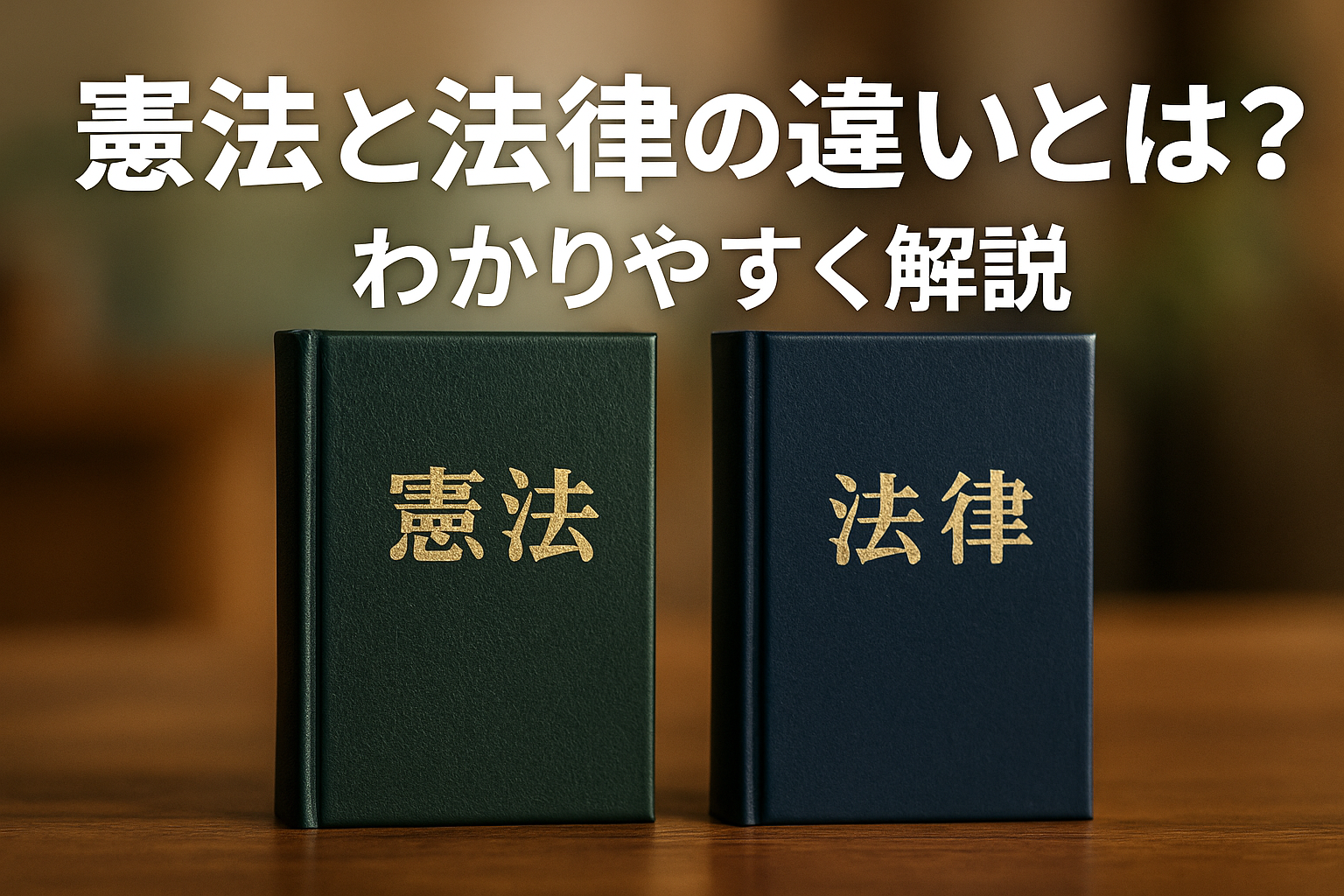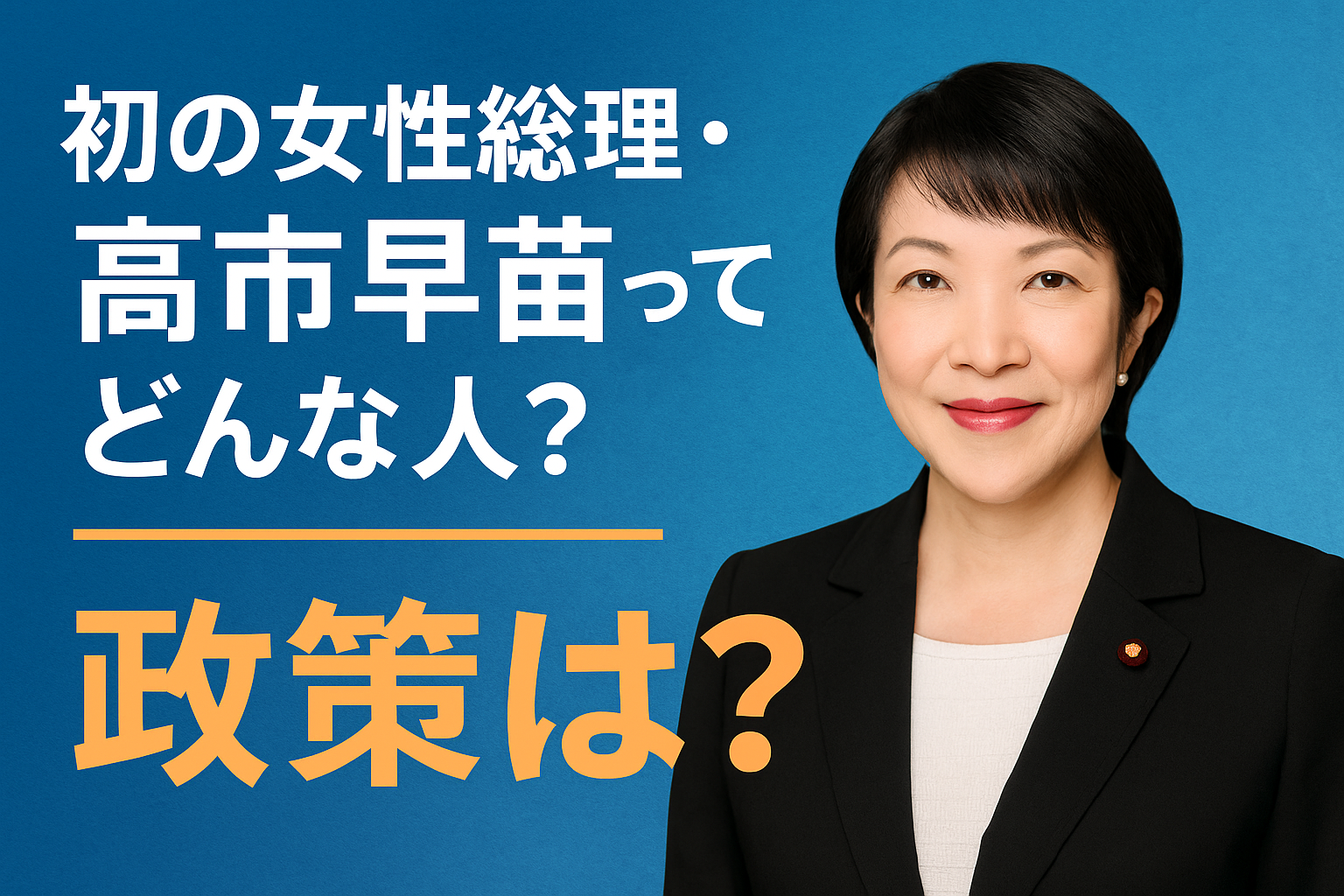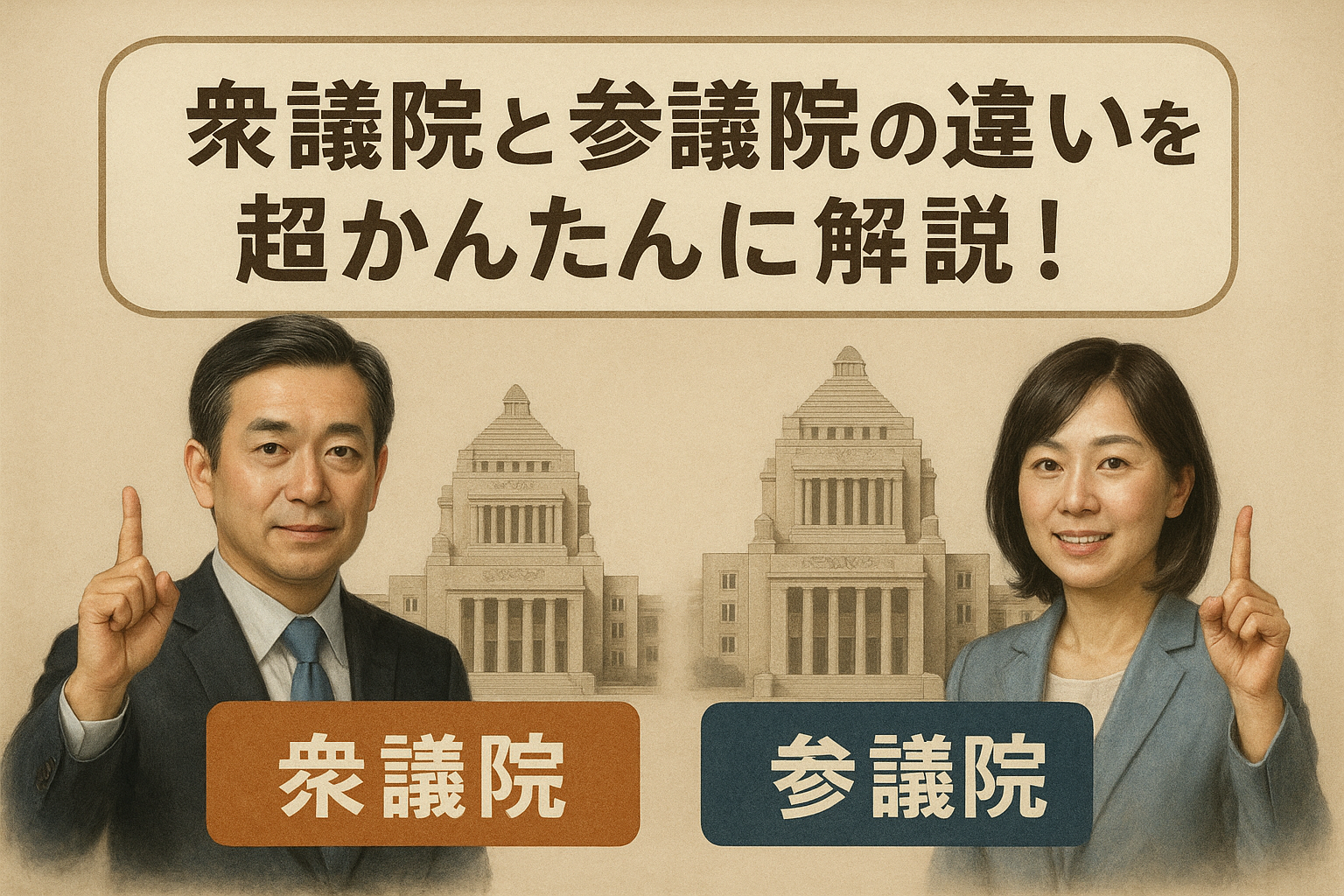三権分立とは?初心者でも5分でわかる仕組みと身近な例をやさしく解説

三権分立ってそもそも何?まずは超シンプルに説明
「三権分立(さんけんぶんりつ)」とは、国の中でとても強い力をもつ役割を3つに分けて、お互いに見張りながら政治を行う仕組みのことです。
三権とは、
- 立法権(りっぽうけん)=ルールをつくる力
- 行政権(ぎょうせいけん)=政治を実行する力
- 司法権(しほうけん)=ルールを守らない人を裁く力
の3つを指します。
もしこの3つの力を1つの人や同じグループが全部もっていたらどうなるでしょう?
たとえば「自分の好きなようにルールを作る」「そのルールに従わなかったら勝手に罰を与える」ということもできてしまいます。
つまり、国民の自由や命までもが危うくなる可能性があるのです。
だからこそ、「力を分けてバランスをとること」が大事なのです。
これが三権分立の基本的な考え方です。
なぜ三権分立が必要なの?歴史と目的をわかりやすく
昔の政治は権力が1つに集中していた
歴史をふりかえると、「王さま」「独裁者(どくさいしゃ)」などが国を全部支配し、国民は文句も言えず苦しい生活をしていた時代がありました。
ルールも政治も裁きも、すべて1人が決められるのでとても不公平でした。
権力が集中すると何が起こる?
気に入らない人をすぐに牢屋へ入れる
自分だけが得をするルールを勝手に作る
国民の意見を聞かずに税金を上げる
こんな政治が実際に昔の国では起きていました。
つまり、力が1つに集まりすぎると必ず悪い方向へ向かうということが世界中でわかったのです。
そこで生まれた「権力を分ける」という考え方
18世紀ごろ、「モンテスキュー」というフランスの思想家が「政治の力を3つに分けよう」と考えました。
それが三権分立のはじまりです。
その後、アメリカやヨーロッパなど多くの国がこの仕組みを取り入れ、国民の自由を守る政治のモデルとなりました。
日本も明治時代からこの考え方を取り入れ、現在の憲法にもはっきり書かれています。
三権分立の「3つの権力」とは?
ここからは具体的に、三権分立をつくっている3つの権力をくわしく見ていきましょう。
立法権(国のルールをつくる)=国会
立法権とは「法律(ほうりつ)」という国のルールを作る力です。
日本では「国会(こっかい)」がこの役わりを持っています。
国会には国民が選挙でえらんだ議員が集まり、法律を決めたり変えたりします。
例え話:学校でいうと「生徒会が学校のきまりを話し合って決める」のに似ている
行政権(ルールに基づいて政治を動かす)=内閣・政府
行政権とは「決まったルールにもとづいて国を動かす力」です。
日本で行政を担当しているのは内閣とよばれるグループで、トップは「内閣総理大臣(総理大臣)」です。
警察・税金・学校・病院など、みんな行政の仕事です。
例え話:ルールをきめたあと、それを実際にどう動かすかの「実行係」
司法権(ルールを守らない人を裁く)=裁判所
司法権とは「ルールをまもっていない人を正しく裁く力」です。
裁判所がその役割を持ちます。
たとえば「法律に反したかどうか」を中立な立場で判断し、「有罪か無罪か」を決めます。
例え話:ケンカが起きたときにどちらが悪いかを公平に判断する先生
三権分立はどう機能している?お互いに監視し合う「抑制と均衡」
三権分立の大きなポイントは「3つが協力しながらも、相手をチェックする仕組みになっている」ことです。
たとえば――
| ○ 立法権 → 行政権をチェック | 国会が内閣の仕事を質問・監視する |
| ○ 行政権 → 立法権へ影響 | 内閣は法律を作る案(法案)を出せる |
| ○ 司法権 → 他の権力を止められる | 違憲判決により法律や行政行為を無効にできる |
このように、どこか1つが暴走しないように、お互いにストップをかけられるのが三権分立の最大の仕組みです。
三権分立は私たちの生活にどう関係している?
「政治のしくみなんて関係ない」と思うかもしれませんが、じつは三権分立は日常生活と深くつながっています。
三権分立が正しく働かないとどうなる?
もし三権分立がなくなったら…
- ルールがむちゃくちゃでも止められない
- 不公平な税金を取られても文句を言えない
- えん罪(やってないのに罪にされる)が増える
- 権力者が国を私物化しても止められない
つまり、自由も命も守れなくなるということです。
ニュースでよく聞く「違憲判決」「国会審議」の意味
テレビやネットで「違憲判決(いけんはんけつ)」と出てくるのは、司法権が行政や立法の暴走を止めている例です。
また「国会で審議(しんぎ)」とは、法律を立法権がしっかり話し合っているということです。
選挙が三権分立とつながっている理由
選挙で国会議員を選ぶ → 立法権を国民が直接決めている
国会が総理大臣を選ぶ → 行政権のトップが決まる
裁判官は一定の条件で国民審査される → 司法に意見できる
つまり、選挙に行くことは「三権分立に参加している」ということなのです。
まとめ|三権分立を一言で言うと?
三権分立とは 「国の力を3つに分けて、お互いに見張りながら国民の自由を守る仕組み」 です。
✅ 立法=ルールを作る
✅ 行政=ルールをもとに社会を動かす
✅ 司法=ルールを守らせる・裁く
この3つがバランスよく働くことで、政治は公平になり、国民の権利が守られます。
もっと知りたい人向けのおすすめステップ
- ニュースを見るときに「これは立法?行政?司法?」と考えてみる
- 選挙のニュースは「立法のメンバーを選ぶこと」と意識する
- 裁判・政治・国会でのやりとりを解説してくれる動画を見てみる
- 学校の社会科教科書で三権分立の図を見てみると理解がさらに深まる
記事全体のまとめ
✅ 三権分立は「立法・行政・司法」の3つに政治の力を分ける仕組み
✅ 目的は「権力が1つに集中して国民が苦しまないようにするため」
✅ 三権はお互いをチェックしながら働き、バランスを保っている
✅ 政治のニュースは三権分立を知ると一気に理解しやすくなる
✅ 選挙に行くことは三権分立に参加し、政治を動かすことでもある
三権分立はむずかしい言葉ですが、本質はとてもシンプルです。
「力を分けて、お互いに見張りながら公平な社会を守る」
この考えを知っておくと、社会の仕組みがよくわかるようになります。